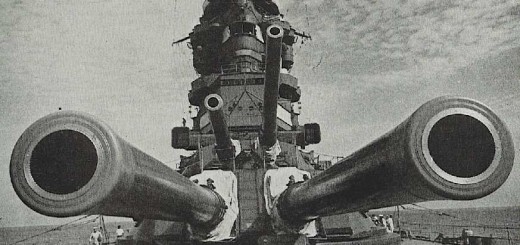列強間の負の連鎖
サライェヴォ事件は衝撃的な事件であったものの、まさかこれが未曾有の大戦を引き起こすとは誰も思っていませんでした。
ヨーロッパ各国は、セルビアの行為を大いに非難し、セルビアの謝罪と一定の賠償は必要であっても、それは両国間で決着すべき事項であり、ヨーロッパの安定に影響を及ぼすようなことにはならないだろうと考えており、夏には各国首脳は例年通りに避暑地に出かけている次第でした。
唯一の懸念は、それぞれの後ろ盾に波及することでした。
セルビアにはスラブ民族の後ろ盾としてロシアが控えており、その介入を恐れたオーストリアにとっては、ドイツの支持が不可欠でした。
果たして、ドイツ皇帝ウィルヘルム2世は、「ドイツは同盟義務と旧来の友好関係に忠実にオーストリアを支持する」と支持を確約し、この無条件支持は「ドイツの白紙小切手」と呼ばれています。
皇太子を殺されて黙っていては国家としての面目が立たないオーストリアは、7月23日にセルビアに最後通牒を突きつけます。
セルビアは一定の譲歩を示したのですが、その態度に不満をつのらせたオーストリアは、7月28日に宣戦布告をします。
宣戦布告後、セルビアとオーストリアの間では第三次バルカン戦争が始まります。
これだけであれば、それまでに行われたバルカン戦争の延長であり、小競り合いで終わるはずでした。
ところが、懸念は的中したのでした。
それも最悪のかたちで。
オーストリアとセルビアとでは、本来国力の差が大きく、単独で戦えばオーストリアが勝つことが明らかでした。
セルビアが負けることは、バルカン半島におけるスラブ系勢力の衰退につながり、ひいてはスラブの盟主であるロシアの地位が弱くなることを意味していました。
したがって、ロシアは黙ってこれを見ているわけにはいかなかったのです。
ドイツはドイツで、オーストリアが勝つと見て、一気に勢力をのばそうと意気軒昂でした。
そんな情勢の中、ロシアはやはりセルビアの支持に乗り出し、7月30日に総動員をかけます。
一方ドイツはこの総動員の撤回を求めますが、これが応じられないと、こちらも8月1日に総動員令を発し、ロシアに宣戦布告します。
ここからが負の連鎖でした。
ドイツの総動員を受けて、隣国のフランスも、露仏同盟にしたがって総動員を開始します。
これを見たドイツは8月3日、フランスにも宣戦布告。
さらに、「栄光ある孤立」を貫いてきたイギリスですが、当初の不干渉方針を翻し、ドイツの大陸ヘゲモニー掌握を阻止するために8月4日にドイツに対し宣戦布告します。
まさに負の連鎖。
列強各国が次々と疑心暗鬼に陥り、戦争体制へと突入していきます。
総動員について
実は外交で解決を図ろうとするイギリスは、ドイツに対し、事前に「ドイツがフランスに攻めこまなければ、イギリスもフランスもドイツに戦争をふっかけない」と伝えていたのです。
しかし、なぜ、それでもドイツは戦争をしかけてしまったのでしょうか。
それには総動員という制度の理解が不可欠です。
総動員とは、軍隊を平時編制から戦時編制に切り替えることを意味します。
予備役を召集し、計画に従って全部隊が戦時編制に切り替わります。
日本では赤紙による召集がよく知られていますが、ヨーロッパでは、役所に張り紙を出し、電報で予備役に動員を通知するのが普通でした。
そして、ドイツの総動員は他の国とは違って、いったん総動員をかけると途中で止めることができないものでした。
モルトケ参謀総長とドイツ参謀本部によって練り上げられたドイツ陸軍のシステムは、動員・集中・開通・作戦が一気通貫されており、そのシステムの精緻さのあまりに、一度発動されてしまった後は君主であっても首相であっても止めることは不可能だったのです。
すなわち、「動員の開始」が「戦争の開始」を意味していたのでした。
そしてその地政学的要素から、ドイツによって起こされた戦争は世界戦争になりかねないのでした。
結局、イギリスの牽制にもかかわらず、こうしてドイツは総動員から戦争開始まで突っ走っていったのです。
これをみた、ロシア、イギリス、フランスも動員を続け、戦争の準備に入っていきます。
かつてであれば、それぞれが親戚同士であるヨーロッパ各国の王族により、意図しない戦争は阻止できていました。
しかし、19世紀に高まったナショナリズムは、国家と国民を一体化させており、いまや王族といえども高まった戦争への意欲を押しとどめる力を持っていなかったのです。
こうして人類が初めて体験する、世界規模の大戦争が始まったのでした。
しかし、それでも各国首脳は、クリスマスまでには戦争は終わるはずと思っていました。
まだこの時点では―――